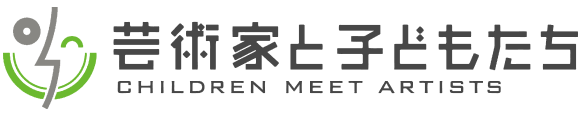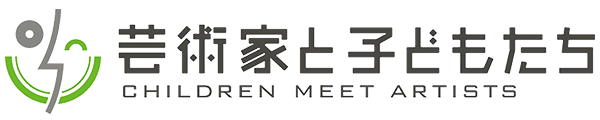にじいろのなかまたち 2019-2020 ~児童養護施設の交流ワークショップ~ vol.3 アーティストエッセイ
Vol.1、2では座談会の様子をご紹介しましたが、vol.3は、アーティストのお二人による、エッセイをご紹介します。
>>プロジェクトの概要を含む、座談会の記事は以下リンクからご覧ください。
画面越しの交流ワークショップ
伊藤寛武(音楽家)
一年前に『にじいろのなかまたち』と、子どもたちが自ら名前を付けたこの企画は、二つの児童養護施設の子どもたち、ダンスと音楽を結びつける交流ワークショップとして始まった。

画面越しにピアニカの演奏を伝える伊藤さん (zoom画面)
このワークショップで目指していたのは、ダンスや音楽を触媒に、子どもたちが自身の思いや感じ方を表に出し、交流する手伝いをすることだった。児童養護施設の子どもたちは、気持ちを出したり発言することを控えてしまうことが少なくない。言葉に出すことができなくても、伝えられることがあり、受け取ってくれる相手がいること。表現の手段はいくつもある、と感じてもらえることを目指した。
2020年度は新型コロナウイルスの流行により、互いの施設を行き来することができない中、4ヶ所をオンライン会議システムで繋ぐ形で開催された。
同じ空間を共有することができない中で、画面越しに何か伝え合うことが出来ないか、子どもたちもアーティストも同じく模索し続けた1年だった。
初めは互いに自己紹介し名前を呼び合うことから始まった。声が聞き取りづらいとき、内容を理解したときは手のサインで伝える。

OKのサインを送り合う (2020年度撮影:伊藤華織)
情報を伝える以前に、あなたのことを見ている、話を聞きたい、という意志を示すこと。画面越しに再開を喜び、覗き込む子どもたちの姿は、情報が溢れていても、意見の押しつけ合いばかりが目立つ現在、交流とはそんなところから始まって、少しずつ進んで行くものだと気づかせてくれた。
画面に映る自分たちの姿を見るという経験は、子どもたちにポジティブな影響を与えた面もある。昨年度身体を動かし、音を出す楽しみを知った子どもたちは、今年度、並んだ画面で自分と相手の動きを見ていたことで、細かい所作の中に人に見せて、何かを伝える表現という意識がより強くなっていた。
1年を通した演目として港大尋の2つの楽曲に取り組んだ。1曲はダンスと歌。もう1曲は楽器と歌と手の振り付けで。
昨年度は歌中心だったが今回は鍵盤ハーモニカ、フルート、ギター、打楽器など楽器を持ち寄り、1つのメロディを演奏した。
楽器を演奏する楽しみとはなんだろう。

ピアニカを奏でる子どもたち(2020年度撮影:伊藤華織)
子どもたちは思い思いの方法で楽器に触れる。同じメロディを演奏しても、短く軽やかに弾く子、のらりくらりと進む子など様々だ。楽器を通し、音だけを聞いてみれば、性別や年齢といった情報は削ぎ落とされ、演奏する者の感じ方が露わになる。
耳を澄まし動きを真似ながら覚えていく。画面越しに指遣いを伝えるのは簡単なことではないが、一足先に覚えた子は自然と新しく参加した子に教えてくれる。
一人ひとり順番にメロディを繋いで演奏してみると、互いの演奏を聞きあって、続く演奏が変化していく。その後、同時に演奏すると、それぞれの感じ方が少しだけ共有され、みんなの音楽ができあがっていた。
トップダウンに組織化された音楽ではなく、口伝えに聞きあいながら形作られていく音楽。画面越しにも向こうの空気が確かに感じられ、最も手応えが感じられた時間だった。
2020年は新型コロナウイルスの年として、誰の記憶にも残るだろう。子どもたちにとっては学校行事がすっかりなくなってしまい、アーティストにとっても公演をすることが難しい困難な年だった。
画面越しのワークショップも同時に音が聞こえず、全身の動きを見ることができず、始める前はいったい何ができるのだろうか、と不安に感じながら準備をしていた。
しかし始まってみれば、子どもたちは画面に映る互いの姿を見て喜び、限られた環境の中で交流の楽しみを次々と見つけていった。
限られた環境で始まった手探りの交流が、子どもたちを支える繋がりになりますように。
きっと残る
セレノグラフィカ 阿比留修一
去年と同じように、秋からひと月に一回会えると信じていた二葉むさしが丘学園とカルテットの交流ワークショップは、未知の感染症の感染拡大の影響で予想外の展開となった。子どもたちや音楽家、スタッフとオンラインワークショップに取り組むこととなった。その中で感じたことを率直に綴っておきたい。

振付の伝え方を工夫しながら踊る阿比留さんと隅地さん(zoom画面)
オンラインでのワークショップを数回体験する中で実感したもどかしさは、いったい何に起因しているのだろうかと考えた。最初の数回については、正直終了後疲労感を覚えずにはいられなかった。対面のワークショップでも、疲労感は無いわけではないが、充実感や喜びの方がはるかにそれを上回るので、疲労感などどこかに消えてしまう。
思い当たる原因はいくつかあった。例えば、画面の向こう側にいる対象よりも、画面に映っている自分のことが気になりがちだと言うことだ。子どもとのやりとりに集中すると、つい画面に近づき過ぎてしまって自分の脚元が映らなくなってしまう。また、自分たちが万全を期して機械操作に臨んでいても、予測不可能の不具合に見舞われることがあり、ワークショップの時間が中断されてしまう。これら二つは、オンラインのシステムに慣れさえすればある程度は軽減されるものだと思う。
けれども、もっと根本的なことが横たわっているのではないかと思うようになった。オンラインの特性でもあると思うが、無言でのコミュニケーションを成立させにくいという点である。これはダンスのワークショップにおいては、というよりも、身体と身体のコミュニケーションにおける根っこのところを脅かす。それを動物的な本能で警戒してしまったというところだろうか。
7回のWSの内、最後の2回は制作スタッフの方が東京からわざわざ京都に来てくださった。
こちらの状況を心配しサポートしたいと思いついたアイデアである。本来ならば私たちが関東圏にある2施設に赴いて子どもたちとWSを通じて交流をしているはずなのに、こちらが関係者を迎え入れるという事は何だか少しばかりこそばゆいような不思議な感覚ではあった。

画面越しに振付を一緒に踊る (2020年度撮影:伊藤華織)
「こうやって毎回のWSの度ごとに移動して来てくださっているんですね。ありがたいことです!」「こうやって子どもたちと一緒に東京から出かけて京都でWSができたらな~って本当に改めて思いました。」
本当に久しぶりにお会いした時になぜか心がホッと溶けるような感覚がした。
オンラインの知識に乏しい私たちに代わって事前にWSの環境を整えてくれたり、また進行中もナイスサポートを…それもありがたいことだったが、この事業を共に大切にしながら進めている仲間が、その身体が傍にあることが何よりも嬉しかった。
今年度を振り返る別事業の座談会の席上で、ある知り合いの美術家が言った言葉がある。「いつか、人とのコミュニケーションをオンラインでしかしない若者たちがでてきますよ…」と。あながち荒唐無稽な予測ではない気もするが、果たしてそんなに簡単なものだろうか。
人はどんな人も身体を持って生まれ、身体を携えて生きて、やがては死んでいく。

「クネクネスリスリ体操」のワークでのふれあい (2020年度撮影:伊藤華織)
切ろうとしても切ることのできない身体との関係性が途絶える瞬間は、片時も無い。人と人との関わりは、その瞬間の連なりのなかで起きることなのだ。このことだけは、その時々の社会の環境やシステムがどのように変化したとしても変わらないはずであるし、そのことの尊厳を、身体で表現するダンスというジャンルのアーティストとして、今後の活動の中でも唱え続けていきたい。
未知の感染症でなくても、私たちがそれまでに馴染んできた日常の変化を余儀なくするものは今後も出現するかも知れない。おそらくその度に少なからず右往左往するのだろう。しかし、人間が健やかに生き抜くために、一番大事な営みはきっと残る。私はそう信じている。
オンラインになったことで、アーティストのみなさんには大変なご負担をかけてしまいましたが、それでも、子どもたちに向き合い、いろんな可能性にチャレンジしてくださいました。そして、職員のみなさんも、一緒に参加しながら、子どもたちのこと、テクニカルのことなど様々サポートしてくださったこと、改めて心よりお礼申し上げます。そして、この子たちとなら、まだまだいろんな未来を考えることができる、そう思える出会いに感謝しつつ、これからの準備を進めたいと思います。来年度の事業にもどうぞご期待ください。
※無断転載・複製を禁ず。